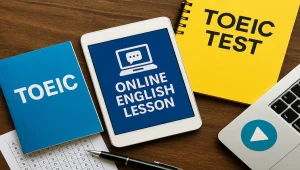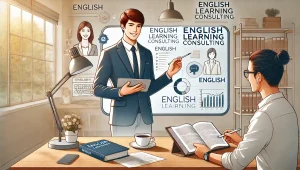英語をこれから学び直したい、あるいは初めて本格的に取り組もうと考えている方の多くが、一度は「英語 学習 順番」で検索したことがあるのではないでしょうか。実際、英語を勉強する順番は学習効果に大きな差を生み出す重要な要素です。
特に「英語を勉強する順番は?」という疑問を抱えている方にとっては、どこから始めて、どのようにステップアップしていけばいいのか明確な指針があると安心です。
文法の勉強の順番を間違えてしまえば、長文読解に苦手意識が残ることもありますし、「文法と長文はどっちが先?」という悩みを抱えたまま進めてしまうと、非効率な学習に陥ることもあるでしょう。
本記事では、英語 勉強 順番 単語の学び方から、目的別に適した参考書の活用方法まで、初心者から再挑戦を考えている社会人まで幅広く対応できる内容をまとめています。また、大学受験を目指す高校生や、中学英語の基礎固めが必要な中学生にも役立つ「年代別の学習順」についても丁寧に解説しています。
自分に合った最適な順序で英語を学ぶことで、効率よく、そして着実に英語力を伸ばすことができます。ぜひこの記事を参考に、あなたに合った学習プランを見つけてみてください。
- 効率的な英語学習の正しい進め方
- 英語文法や単語を学ぶ順番の重要性
- 学習者の年代や目的別に適した順序
- 参考書の活用タイミングと選び方
英語を学習する順番の正しい進め方とは
- 英語を勉強する順番は?初心者の基本ステップ
- 文法の勉強|順番を間違えないために
- 単語はいつ覚えるべき?
- 文法と長文はどっちが先?学習効率を上げる考え方
- 参考書はどの段階で活用するべきか
英語を勉強する順番は?初心者の基本ステップ

まず最初に意識すべきことは、「順番によって学習効果が大きく変わる」という点です。英語の勉強は、やみくもに始めるよりも、正しい順序で進めた方が、理解も定着もスムーズになります。
初めに取り組むべきは「発音」です。英語の音に慣れることで、その後に続くリスニングやスピーキングの精度が大きく変わってきます。日本語に存在しない音や発音記号を学ぶことで、英語の音を正しく認識できるようになり、単語の聞き間違いや意味の取り違えが減ります。
次に必要なのは、語彙と文法の基礎を固めることです。ただ単語を丸暗記するのではなく、文法の中で使われる例文と一緒に学習することで、より実践的な知識として身につけやすくなります。
その後に進むべきは、リーディングやリスニングなどの「インプット系」の練習です。読み聞きできる力があってこそ、次のステップであるライティングやスピーキング、つまり「アウトプット系」の練習が生きてきます。
このように段階を踏むことで、英語を「理解し、使える」力が育ちます。焦って会話練習から始めるのではなく、土台をしっかり作ることが、結果的に最短で上達するための近道と言えるでしょう。
文法の勉強|順番を間違えないために
文法を学ぶ際に大切なのは、「どの順にどの文法を学ぶか」を意識することです。英語には多くの文法項目がありますが、それらを効率よく理解するためには、基礎から応用へと段階的に進めることが重要です。
最初に学ぶべきは、be動詞や一般動詞、基本的な現在形・過去形の使い方です。これらは日常会話や基礎文作成の土台となるため、ここがあいまいなままでは、以降の学習がスムーズに進みません。
次に進むべきは、助動詞・疑問文・否定文といった文の組み立てに関わる項目です。これにより、自分の意思や質問、否定などを表現できるようになります。そこから、時制のバリエーション(現在進行形・現在完了など)や比較・受動態・関係代名詞といったやや複雑な文法に進むとよいでしょう。
注意すべき点としては、一気にすべての文法を覚えようとしないことです。一度に詰め込みすぎると混乱しやすく、定着も難しくなります。1つずつ理解し、例文で確認しながら進める方法が効果的です。
また、単にルールを暗記するだけでなく、声に出して練習したり、簡単な英文を自分で作ったりすることで、実際に使える文法として定着させることができます。こうしたアウトプットを並行して行うことで、文法の知識が確かなスキルへと変わっていきます。
単語はいつ覚えるべき?

単語の学習は、文法の基礎をある程度理解してから始めるのが効率的です。というのも、単語だけを先に大量に覚えても、それを使って英文を組み立てる力がなければ、実践で役立ちにくいためです。
まずは中学レベルの文法を使って簡単な文章が作れるようになってから、頻出の単語を覚えていくと、学んだ単語の使い方がより明確になります。この段階で覚えるべき語彙数は、2,000〜3,000語程度が目安です。日常英会話や基礎的な文章の理解にはこの範囲で十分対応できます。
また、単語を覚える際は、単語単体で覚えるよりも、例文とセットで学ぶことをおすすめします。例えば「enjoy」という単語なら「I enjoy reading books.」といった例文で覚えることで、単語の使い方や文の構造が一緒に身につきます。
ただ、全く単語を知らずに文法だけを学ぶのも非効率です。そのため、文法学習中に出てきた単語は、その都度覚えていく姿勢が大切です。こうすれば、語彙力と文法力をバランス良く伸ばせます。
つまり、単語の勉強は文法の理解をベースにしつつ、並行して進めるのがベストです。いきなり単語帳を最初から全部覚えようとするよりも、文法とセットで使いながら覚える方が、長期的に見て定着率が高まります。
文法と長文はどっちが先?学習効率を上げる考え方
どちらを先に学ぶべきか迷ったときは、文法を優先するのが基本です。なぜなら、文法の知識がなければ、長文を読んでも正確な意味を把握しにくくなるからです。
例えば、「He had been studying for three hours.」という文を読んだときに、過去完了進行形のルールを知らなければ、「彼がどれくらいの時間勉強していたのか」や「いつのことなのか」といった情報を正しく理解できません。つまり、文法は長文を読むための「土台」となります。
一方で、文法を一通り学習した後は、積極的に長文読解に取り組むべきです。長文には多くの文法事項が自然な形で含まれているため、実際に使われる文の中で文法を再確認できるというメリットがあります。
また、文法学習ばかりを続けていると、「実際に使う英語」の感覚がつかみにくくなります。そのため、文法を学んだあとは、適切なレベルの長文を読むことで、理解の定着や応用力が養われます。
前述の通り、文法を先に学んだ方がスムーズですが、その後に長文を活用して「実践力」に変えていく。このステップが、英語学習の中でとても効果的な流れになります。
参考書はどの段階で活用するべきか
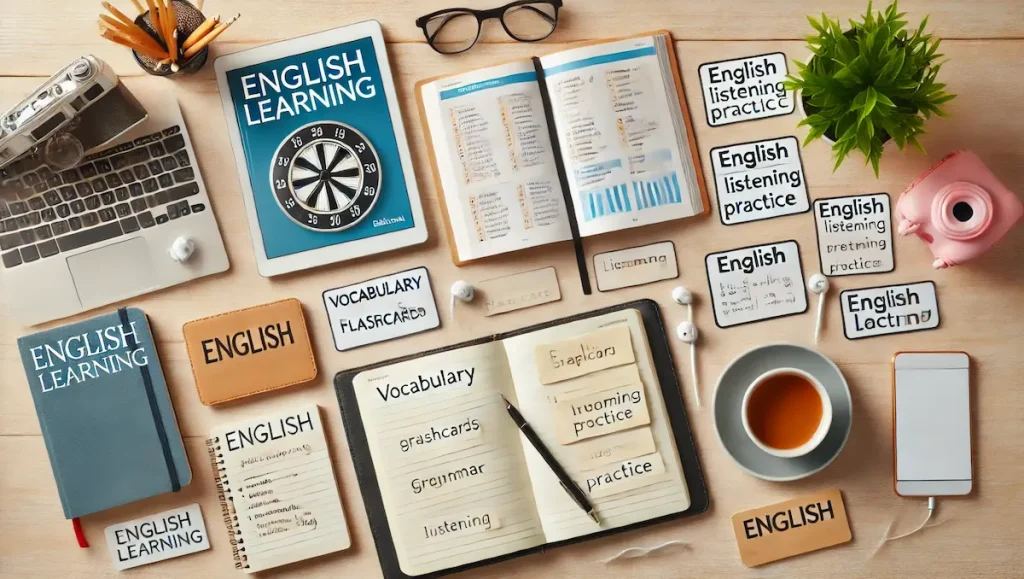
参考書は、学習の段階に応じて使い分けることが大切です。いきなり難しい内容に取り組んでも挫折しやすいため、今の自分の理解度に合ったレベルを選ぶ必要があります。
初学者であれば、まずは発音や文法の基礎を学ぶための参考書からスタートしましょう。このとき、説明がやさしく、例文が豊富なものを選ぶと理解しやすくなります。また、イラストや図解があるものは、抽象的な概念もイメージしやすくなります。
文法の基礎がある程度固まった段階では、語彙や読解の参考書にシフトしていきます。語彙に関しては、単語だけが羅列されたものよりも、例文や発音記号が載っているタイプの方が実用性があります。
さらに、長文読解やリスニングの練習には、模試形式の問題集や過去問を含んだ教材が効果的です。このときも、いきなり難関レベルのものに手を出すのではなく、少しずつレベルを上げていくことが成功のポイントです。
また、すべての参考書を一度に使う必要はありません。学習の目的ごとに必要なものを絞り込み、少数を繰り返し使い込む方が、内容を深く理解できます。
このように、参考書は「タイミング」と「目的」によって使い分けることが大切です。単に評判が良いものを選ぶのではなく、自分の学習段階に合ったものを選ぶ視点を持ちましょう。
英語学習の順番は目的と年代で変わる
- 大学受験に適した順番とは
- 社会人におすすめの順番
- 高校生のための効果的な順番
- 中学生が押さえるべき順番
- 学習目的別で異なる順番の考え方
- 忙しい人向けの効率的な順番とは
大学受験に適した順番とは
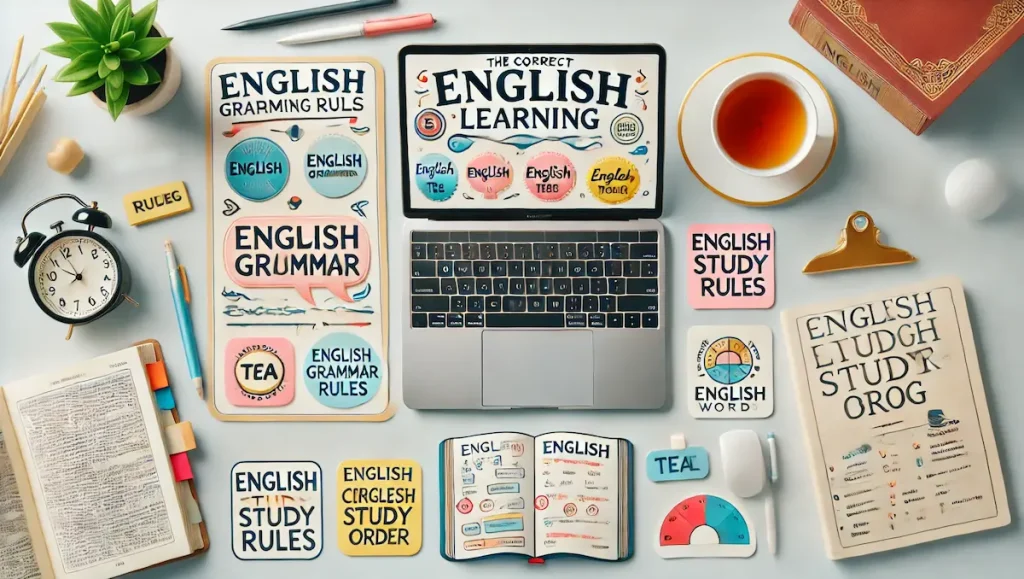
大学受験を見据えた英語学習では、段階的かつバランスの取れた順番で進めることが鍵となります。試験では幅広いスキルが求められるため、基礎の積み上げと応用力の養成がどちらも必要です。
まずは、文法と語彙の基礎をしっかり固めることから始めます。中学〜高校初級レベルの文法を理解し、基本的な単語を覚えることが最優先です。多くの大学入試では、正確な英文理解が求められるため、この段階を飛ばしてしまうと読解でつまずく原因になります。
その後、リーディング力を高めるために長文問題に取り組みます。最初は短めの文章から始め、徐々に語数を増やすと無理なく対応できるようになります。文章の中で見つけた文法や語彙を復習することで、知識の定着も期待できます。
次のステップとしては、リスニングやライティングの対策です。最近では、入試にリスニングを含む大学も増えており、実際の音声に慣れておくことが欠かせません。シャドーイングやディクテーションを取り入れると効果的です。
ライティングについては、自由英作文や要約の練習を通じて、自分の意見を英語で表現する力を養いましょう。テンプレート的な構文を覚えると、安定した文章を書きやすくなります。
また、志望校によって出題傾向は異なるため、過去問や模試を通じて早い段階から傾向分析をしておくと、学習の優先順位をつけやすくなります。
このように、大学受験に向けた英語の学習は、基礎から応用までを段階的に進めることが最も効果的です。焦らず一歩ずつ積み重ねることが、合格への近道になります。
社会人におすすめの順番
社会人が英語を学ぶ場合、限られた時間の中で効率よく力をつけることが求められます。そのため、順番を意識した学習計画が欠かせません。
まず取り組むべきは「発音とリスニングの強化」です。仕事で使う英語は「聞いて理解し、伝える」ことが中心になるため、英語の音に慣れることが最優先です。特に、ビジネス英語ではカタカナ英語とのギャップが大きいため、英語特有の音を正確に聞き取る力が必要です。
次に必要なのは、日常業務でよく使う「表現や語彙」の習得です。例えば、メールや会議、電話対応などで使われる定型表現は、事前にフレーズ単位で覚えておくと即戦力になります。この段階では、単語帳よりも実用的なフレーズ集や英語ニュースの音読が効果的です。
文法の学習は、実際に使う中で気づいた「間違いや曖昧な部分」を補強する形で進めると効率的です。ゼロからすべての文法を網羅するよりも、自分にとって必要なルールだけを重点的に復習する方が時間対効果は高くなります。
アウトプットの段階では、英会話アプリやオンライン英会話を使って、実際に英語を使う練習を積むことが大切です。忙しいスケジュールの中でも、1回10分など短時間でできる環境を作ることで、継続しやすくなります。
社会人の場合、学習時間が限られていることが多いため、全てを完璧にするのではなく、必要なスキルに絞って戦略的に学ぶ姿勢が成果につながります。
高校生のための効果的な順番

高校生が英語を学ぶ目的は、大学受験だけでなく将来的な実用性も視野に入れた総合的な力をつけることです。そのため、順を追った体系的な学習が必要になります。
最初にやるべきは「中学英語の復習」です。高校英語は中学内容を前提に進むため、もし中学の基礎が不安定であれば、ここを見直すことがスタートラインになります。特に、時制や助動詞などの基本文法は繰り返し出てくるため、早めに固めておきましょう。
その次に取り組むのが、「高校レベルの文法と語彙」です。文法に関しては、学校で使っている教科書や問題集に加え、解説が丁寧な参考書を使って自主的に補強していくと理解が深まります。語彙は、日常単語だけでなく、受験で頻出の抽象的な単語にも触れていく必要があります。
リーディングとリスニングは、ある程度語彙と文法の知識が定着してから本格的に取り組むのが理想的です。前述の知識があることで、英文の意味をつかみやすくなり、読解や聞き取りのスピードも自然と上がります。
ライティングやスピーキングについては、英語の文章を自分で作る力を養うステージです。英作文やスピーチ練習を通じて、覚えた文法や単語を使える形に変えるトレーニングを行いましょう。
高校生の学習には時間的な余裕がある反面、部活動や定期テストなどで忙しくなることもあります。そのため、無理のないスケジュールを組み、毎日少しずつでも英語に触れる習慣を持つことが効果を高める鍵になります。
中学生が押さえるべき順番
中学生が英語を学ぶときは、学校の授業に合わせつつ、英語の「使い方」にも目を向けた順番で学習を進めるのが効果的です。ただ教科書を暗記するだけでは、英語が実際に使えるようにはなりません。
まず最初に取り組みたいのは、アルファベットやフォニックスを含めた「発音の基本」です。英語の音の仕組みを理解しておくと、その後のリスニングや単語の暗記がぐっと楽になります。例えば、「th」や「v」など、日本語にない音は早いうちに慣れておくことで、発音のクセがつきにくくなります。
次に進むべきは、「基本文法」と「語彙の習得」です。中学で学ぶ文法は、英語学習の土台となる重要なルールばかりです。主語と動詞の関係、疑問文の作り方、時制の変化など、日常会話やテストで必要な知識はここに集約されています。語彙についても、まずは教科書に出てくる単語を確実に覚えることが優先です。
さらに、「読む・聞く」のインプット学習にも早い段階から取り組んでおきましょう。音声付きの教科書や英語アプリを使って、自然な英語のリズムやスピードに触れることが、苦手意識を減らす近道になります。
最後に、「書く・話す」のアウトプットに挑戦します。短い英作文や自己紹介、好きなものを伝える練習から始めると、英語を使う楽しさが感じられ、学習のモチベーションにもつながります。
このように、中学生のうちから段階的に英語に触れておくことで、高校以降の英語学習がスムーズになります。
学習目的別で異なる順番の考え方
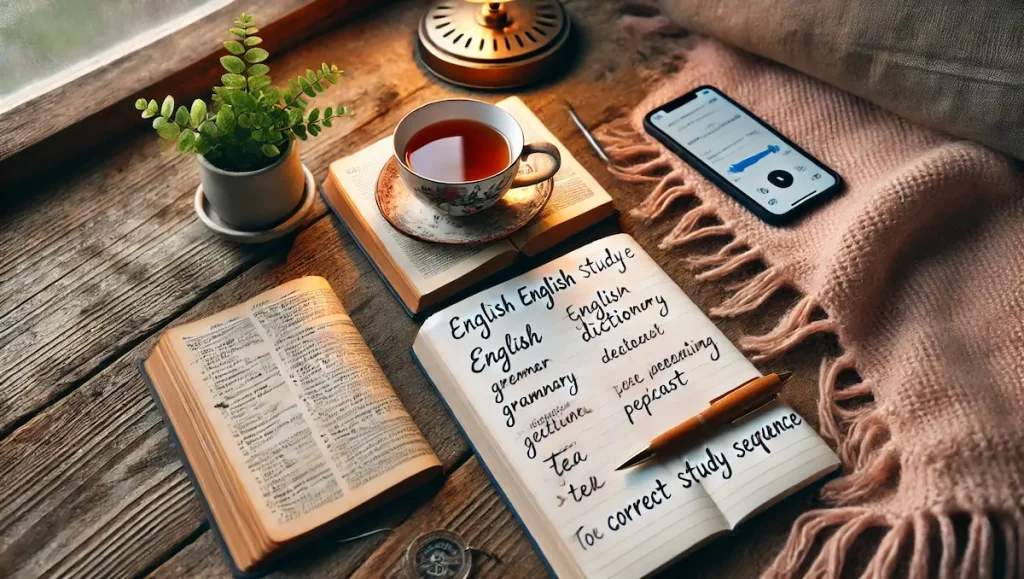
英語を学ぶ目的によって、最適な学習順序は大きく変わります。すべての人に同じ順番が当てはまるわけではありません。だからこそ、自分がなぜ英語を学ぶのかを明確にすることが、最初の一歩になります。
例えば「海外旅行で困らない程度に話せるようになりたい」という人の場合、難しい文法よりも、よく使う表現やフレーズを覚える方が効果的です。この場合は、発音と会話練習を最初に重点的に行い、必要な語彙を増やすことで実践的なスキルが身につきます。
一方、「資格試験に合格したい」という人には、文法・語彙のインプットが不可欠です。TOEICや英検では、文法的な正確さや長文読解の力が問われるため、地道な基礎力の積み上げが欠かせません。この場合、アウトプットよりも読解・リスニングの比重を大きくするのが現実的です。
さらに、「仕事で英語のメールや会議が必要」という場合は、リーディングやライティングからスタートし、次にリスニング・スピーキングといったアウトプットを強化する流れが理にかなっています。ビジネス英語の特徴は、表現がある程度パターン化されているため、頻出フレーズを押さえることが優先されます。
このように、目指すゴールによって、どのスキルをどのタイミングで強化すべきかは変わります。目的を定めたうえで、学習の順番を柔軟に調整することで、効率よく成果を出すことができます。
忙しい人向けの効率的な順番とは
毎日が忙しく、まとまった学習時間が確保しにくい人にとっては、「短時間で効率よく学べる順番」を意識することが重要です。ポイントは、すべてを完璧にこなすのではなく、「優先順位」と「継続性」を重視した学習ステップを組み立てることです。
最初に取り入れたいのは、英語の「音」に慣れることです。通勤時間や家事の合間に英語音声を聞くことで、耳を英語に慣らすことができます。このとき、ニュースや映画ではなく、初心者向けの短めな音声教材やアプリを選ぶと理解しやすくなります。
次に取り組むべきは、文法の基礎をざっくりと確認することです。ただし、すべてを暗記しようとするのではなく、自分がつまずきやすい文法だけをピックアップして学び直すのが現実的です。たとえば、過去形や助動詞など、日常会話でよく使う項目に絞ると学習時間を短縮できます。
語彙の学習は、隙間時間を活かして進めましょう。1日10個でも、アプリを使って音と一緒に覚えるようにすると記憶に残りやすくなります。また、実際に使う場面をイメージしながら覚えると、より定着が深まります。
インプットに慣れてきたら、短い時間でできるアウトプットも取り入れます。5分だけでも英語で日記を書いたり、スマホに向かって話す練習をしたりすることで、学んだ内容が実践で使えるようになります。
このように、忙しい人ほど「完璧を目指さない学習順」と「毎日続けられる仕組み」が大切です。英語は一度に詰め込むのではなく、毎日の積み重ねで確実に身についていきます。
英語学習の順番の正しい進め方まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 発音の習得が最初のステップとなる
- 文法はbe動詞や現在形から段階的に進める
- 単語は文法学習と並行して覚えるのが効率的
- 単語は例文と一緒に覚えると定着しやすい
- 長文読解は文法の基礎習得後に始めるべき
- 長文を読むことで文法の実践的理解が深まる
- 参考書はレベルに応じて段階的に使い分ける
- 難しい参考書は避け、自分に合うものを選ぶ
- 大学受験では文法と語彙の基礎固めが重要
- リスニング対策にはシャドーイングが効果的
- 社会人はリスニングと発音を優先的に学ぶべき
- ビジネス英語では定型表現の習得が役立つ
- 高校生は中学英語の復習から始めるとよい
- 中学生は発音・文法・語彙の順で習得すべき
- 学習目的に応じて柔軟に順番を調整する必要がある